「安全保障の議論は専門家だけに任せない方がいい」小泉悠氏はなぜそう思うのか
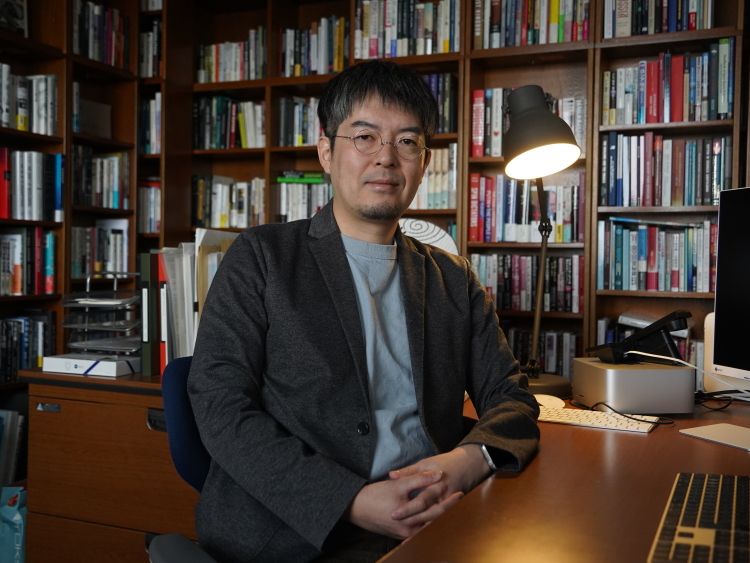
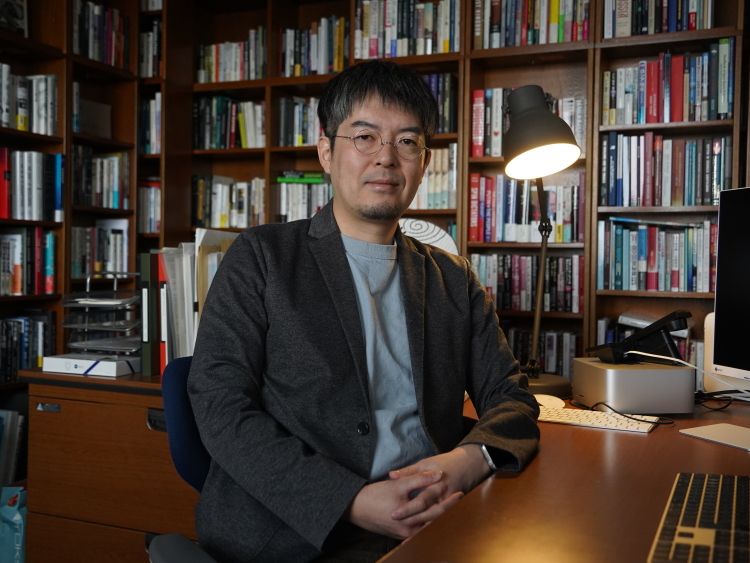
――第2次世界大戦が終わり、また冷戦の終結を受け、様々な国で徴兵制が消滅した。なのに再び欧州、中東、そしてアジアでも徴兵制が復活・拡大する動きが顕在化しているのは、なぜなのでしょうか。
やはり軍事的な緊張の高まり、国家間の問題解決の手段として大規模な国家間戦争をやるという現実味は、1990年代、2000年代にはなかった。私の学生時代も、そうしたことが起きる可能性は否定しないが、極めて起こりにくいという教育を受けた覚えがある。それから20年経ってみると、ロシア・ウクライナとの間で、フルスイングの国家間戦争が3年も続いている。

もちろん、これまでもイラク戦争やユーゴスラビア戦争などがあったが、圧倒的な力を持つ有志連合が一方的に、国際秩序を脅かした国をたたくこともあったが、それは戦争というより懲罰に近かった。
それがロシア・ウクライナ戦争では、古典的な戦時動員、戦時増産を行い、世界中から軍事援助をかき集めて3年も戦闘を続けている。第1次世界大戦に本当によく似てきている。規模は当時に比べてまだ小さいかもしれないが、本当に国家間戦争が起きる、ということを目の前で見せられた。
日本でも、安全保障のために自衛隊を強化すると言うと、「資源のない日本に、誰が攻めてくるんだ」という議論があった。だが、そういう事情がなくても、現実にウクライナがロシアに攻められている。なので日本もハリネズミのように(専守防衛で)武装すればよいとは思っていない。大戦争に備えることを真面目に考えなくていい、というこれまでは、幸せな時代だったのではないか。
――ただ、トランプ米政権が北大西洋条約機構(NATO)加盟国に国内総生産(GDP)比5%まで防衛費を増やすよう要求する一方、トランプ氏のロシアのプーチン大統領への接近に危機感を募らせた欧州では、核をめぐる議論が活発化しています。
単純化して言えば、米国の拡大抑止は信用できず、ロシアの核戦力に対抗できないという危機感があるのだと思う。冷戦期の欧州の国による米国との核シェアリング(共有)というのは、米国がドイツやイタリアに独自に核保有させないよう、なだめるためにやっているところがある。米国はあなた方の爆撃機に搭載する核弾頭を貸すので危機の時はこれを使用してくれと。
ところが、その米国の欧州への関与がもはや怪しくなってきた。米国は同盟国防衛の義務を負うことに嫌悪感すら抱き始めていると。これは逆に欧州側から見ると、もう米国(の拡大核抑止)を前提とした対ロシア抑止はできなくなるのではないかという懸念がある。
――日本でも、保守派や自衛隊幹部出身者のなかで、核保有論がくすぶっているように思います。
これまで日本では、核に関する選択肢というのは、視界になかった。ところが、3年前のロシアによるウクライナ侵攻があっても、米国は戦車さえ出そうとしなかった。さらにトランプ氏が当選を決める前後の半年間で、急速に「核」が視界にチラチラと入り始めたという感じがする。米国の拡大抑止が信用できず、中国やロシア、北朝鮮の軍事的脅威が除去されないとなると、核武装というのが視野に入ってくる。ただ、ではどんな核武装ができるのかということが問題だ。
仮に、日本が一隻で100前後の目標を攻撃できる核搭載のSSBN(戦略ミサイル原子力潜水艦)を保有したとしても、海に1隻、2隻いたところで、中国やロシアへの(軍事施設や核兵器を狙う)カウンターフォース攻撃には足りない。
一方、民間目標を狙うにしても、(核兵器の致命的な破壊力を背景に、核保有国が互いに核攻撃を思いとどまらせる)「相互確証破壊」にはなり得ない。中国やロシアが国家として崩壊するわけではないが、政治的に受け入れ難い打撃を与えることを目指す「相互確証報復」戦略をとるしかない。
それはつまり、数十万人から数百万人規模の中国人やロシア人を殺す能力を持つことを意味するが、日本の国策として目指すべきなのかと言われると、私は非常に人間としてためらってしまう。「確証報復」型の核戦略では、尖閣諸島や先島諸島への限定攻撃も抑止しきれない。低出力核からの段階を刻んだエスカレーション・ラダー型の核戦力を持たなければならないが、それは日本にとって現実的ではない。核さえ持てば抑止力になるというのは、私は幻想だと思っている。

――日本では、戦略的視点に基づいた議論が軽視されているということですか。
右でも左でもよいが、核兵器や核戦略についてゴリゴリに勉強した上で批判するという言説が日本では薄い。かつて(米国の天文学者でSF作家の)カール・セーガンが著書「核の冬」で核抑止論批判をやり、米国の核戦略の専門家と論争しているが、非常によく勉強している。ウィリアム・ペリー元米国防長官ら、実際に核をあずかった人たちからも核抑止論批判があり、めちゃくちゃリアルなので、傾聴に値する。日本も戦争被爆国として二度とこのような惨事を繰り返してはいけないという核兵器批判は途絶えさせてはいけない。
一方で、ゴリっと核戦略を学んだ人たち同士での対話もないといけない。私は日本は核を持たない方がよいと思うが、核を持たないのであれば、どのように米国の拡大抑止を引っ張りこんでおくのかという議論を同時にしないと無責任だと思う。その時に、核シェアリングというのは、選択肢になるのか。政治的な宣言効果はあるのだろうと思うが、米国の拡大抑止が信用できないと言っている時に、米国の核弾頭を日本に置くことにどれだけの意味があるのか、根本的に疑問だ。
――自衛官の人手不足も深刻です。対中脅威論が高まっているなかで、どう対応すべきだと思いますか。
軍人の人手不足というのは世界的な現象だ。社会が成熟すると、軍人という仕事がなかなか選ばれなくなる。対中脅威論の高まりについては、日本の隣国でこれだけ急速に軍事力を増強している国があるだから、それに対する警戒感が増すのは仕方ないことだ。中国は通常戦力だけでなく、核戦力をものすごい勢いで増やしている。
「2027年に台湾有事」みたいな話もあるが、オリンピックじゃないんだから、そんなこと分かるわけないと思う。その2027年にそういうことを起こすも起こさないのも我々次第ですから。一つは、中国に「そんなことはやらない方がよい」と(外交で)働きかけることだし、もう一方で、「有事を起こそうとしても無駄ですよ」という態勢を我々の抑止力でつくる。その意味で、私は防衛力強化には賛成。ただ、この防衛力の強化は、勇ましく、うれしそうに語る話ではないと思う。
定員割れが続く自衛隊にあって、いまの情勢をみて、いきなり徴兵制に踏み込むというのは早すぎる。ただ、本格的な有事となれば、日本だって純軍事的に言ったら、徴兵制という議論が起きかねない。だから、安全保障の議論は、安全保障の専門家だけに任せない方がよい、というのが私の正直な思いです。
徴兵制というのは、人を集めるだけでなく、国防意識を高めるために必要なんだ、何のために、何と戦うかを国民に理解させるために必要なんだというのは、結局、大日本帝国時代の軍国教育じゃん、と見えてしまう。
民主主義を守るために国防や安全保障を考えるわけで、民主主義を守るためだと言って軍国主義に戻るのであれば、それはまったくの本末転倒だと思う。我々は何のために国防をやるのかという価値観と、軍事合理性をてんびんにかけながら考えなければいけないのであって、軍事的合理性だけを追求するなら、「理想型は北朝鮮」という話になってしまう。