欧州で目立つ徴兵制の復活 兵器の無人化が進む中、小泉悠氏が考える軍事力の本質とは
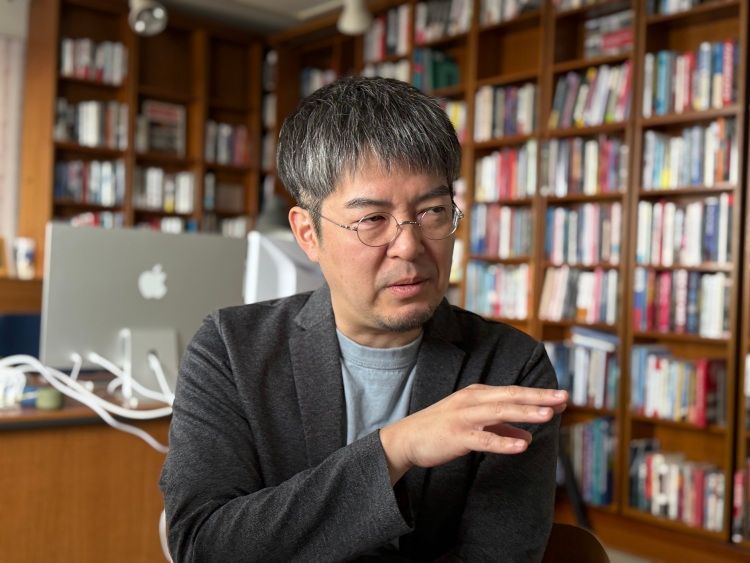
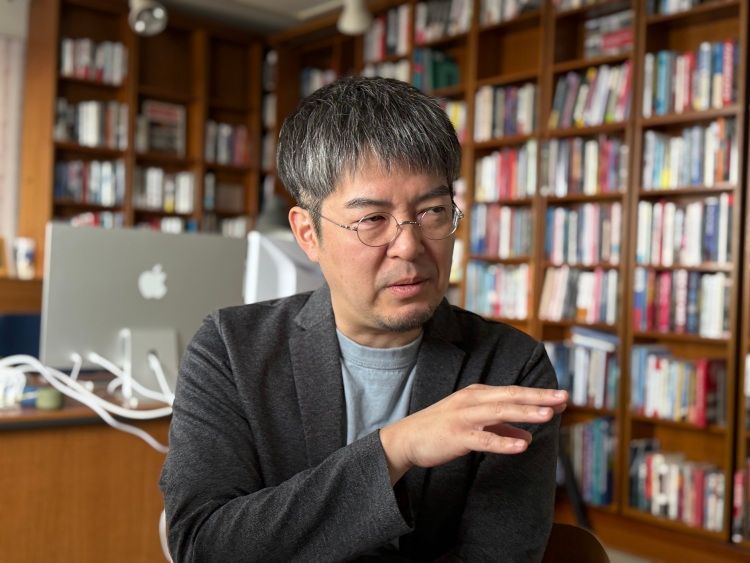
――ロシア・ウクライナ戦争では、軍の省人化につながると見られるAI・無人兵器などハイテク兵器が本格的に投入されていますが、両国とも兵士不足が深刻で動員に苦慮しています。これはなぜでしょうか。
二つの側面から説明できる。まず技術的な側面から話をすると、無人兵器といっても完全な自律型兵器でない限り、それを操縦し、整備する人員が必要になる。無人地上車両(UGV)も同じだ。「無人兵器を導入する」ことが、イコール「人手が減る」というわけではない。
米特殊部隊の無人機戦略の最前線を描いた「ドローン情報戦」という本があるが、CIA(米中央情報局)が現地で協力者を集め、標的となる人間の立ち回りや人間関係を血眼になって調べあげるなど散々人手を割いた上で、ドローン攻撃するのは最後の最後、という世界が描かれている。
一方、「軍事力とは何か」という本質論で考えれば、物理的に相手を力でねじ伏せること。その本質は「数」だ。どうやったら多くの兵士を集められるか。それが徴兵制だ。ロシアの伝統的な軍事的思想では、技術に投資するよりも、重要なのは徴兵制で、その徴兵制度は、軍事的な社会制度を維持するのに必要という考え方がある。

――戦争の勝敗は、ハイテク兵器でなく、兵士の数で決まると言うことですか。
ロシアでも二つの異なる主張がある。ロシア軍事科学アカデミーの総裁で陸軍大将のマフムト・ガレエフ氏が1995年に「何が武力紛争の本質を変えるのか」という副題の本を出していて、次の戦争は大々的にロボットを使うようになると、軍事技術の発展について、ほぼ正確に予想している。AIや極超音速兵器、サイバー戦についてもガレエフ氏の頭の中に入っている。しかし、本丸は、古典的な軍事力である「兵力」でなければならないと主張している。
一方、同じ軍事科学アカデミーの副総裁だったウラジミール・スリプチェンコ少将は、ガレエフ氏の部下だが、言うことが全然違う。次の戦争はテクノロジーが勝敗を決める。兵士の量は重要ではなくなり、「陸軍を軍種として廃止してしまってもよい」と。精密誘導兵器や無人機、ステルス爆撃機、宇宙システムなどが次なる戦争を決定づける力になるという議論を展開している。
――どちらが正しいのでしょうか。
それは戦われる戦争の性質によって異なるのだと思う。ロシアが歴史的に何度も経験してきた陸上戦であれば、やはりガレエフ型になる。それは今のロシア、ウクライナ両軍が証明している。細かい小手先の技術よりも、兵士の量が決め手となる。この3年間の戦争の後半で、ロシアが最終的に優勢を獲得していったのは、やはり大量の兵士の動員に成功した部分が大きい。
一方、ウクライナがこの3年負けなかったのも、量を確保できたから。双方とも徴兵制があったからということが大きいと思う。ただ、海での戦いとなると、圧倒的に技術の優劣が勝敗を決する。軍艦のなかったウクライナの海軍が水上ドローンなどで攻撃し、結局ロシアの黒海艦隊をたたき、セバストポリから追い出した。
――ロシアとウクライナでは双方が技術を駆使した戦い方をしているが、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ攻撃では、投入される軍事技術の差が武装組織ハマスとは歴然としています。それなのに、イスラエルでも兵士不足が深刻化し、徴兵制を拡大しているのは、なぜなのでしょうか。
イスラエルの場合、空軍力は平時の人数で回している。空軍は一番テクノロジーに敏感な軍種で、簡単に減らしたり、増やしたりしにくい。一方、イスラエルが予備役動員を行って兵士を増やしているのは、ガザで地上戦を始めたからだ。しかも対ゲリラ戦で長期にわたって占領しなければならない。
対ゲリラ戦は人手が必要になる。正規軍同士の戦いなら、戦線がある程度はっきりしているが、ゲリラ戦は相手がどこから出現するのかも分からない。どれだけロボット化しても、現状ではロボット化しきれないのが、人間の兵隊ということなのだと思う。
我々人類は、陸生動物だから、最後に、陸の上を兵隊のブーツが踏みつけないと勝負が決まらない。海空は、ロボット兵器だけで勝ち負けを決めることができるかもしれないけれど、陸の戦いでは、人間でないと、土地を占領するという機能が果たせない。
