世界に広がるファクトチェック 巨大ITとの連携は? BBCとAFPの担当者に聞く
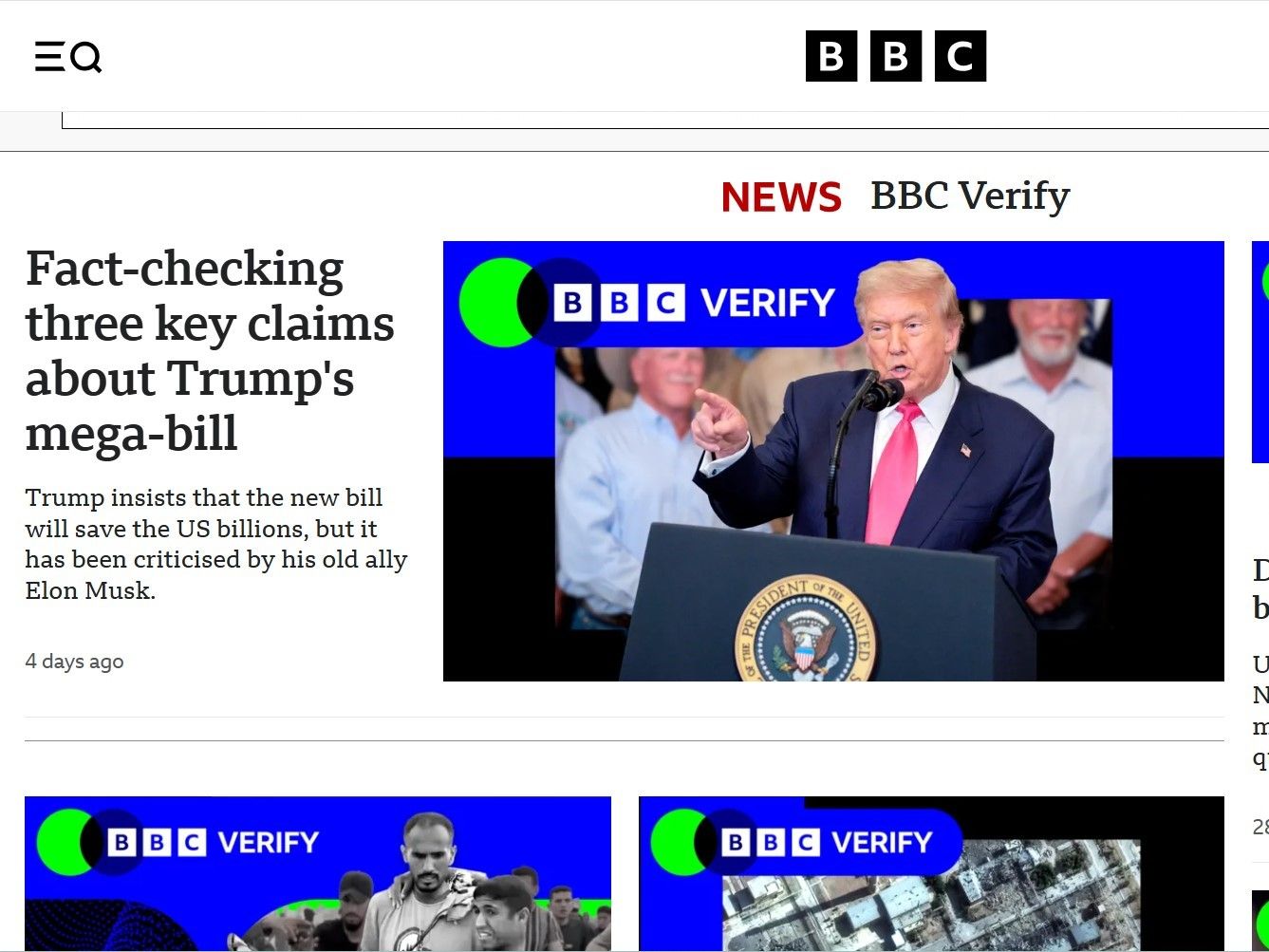
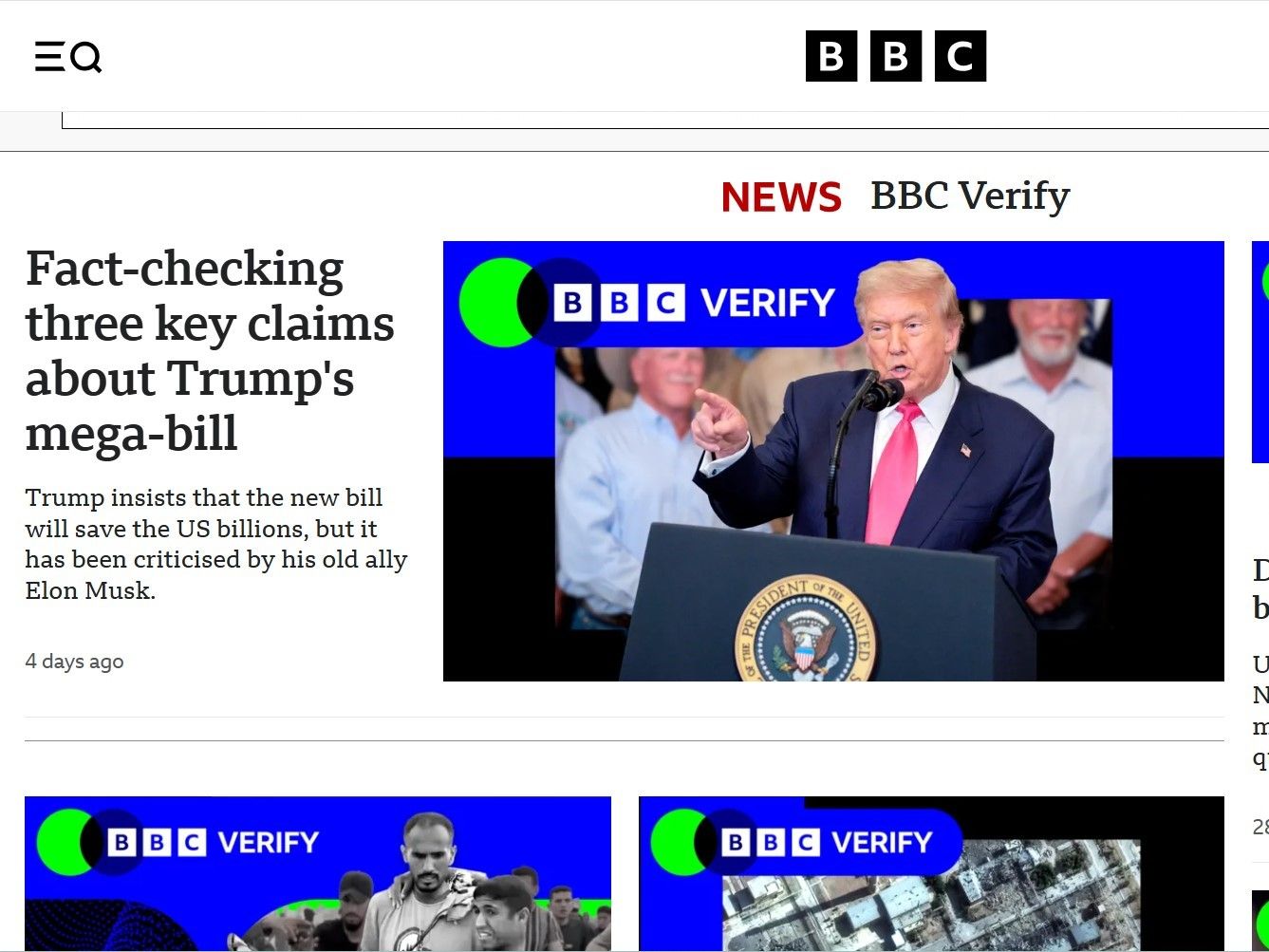
――BBCはいつから、なぜ偽誤情報への対策に力を入れ始めたのですか?
事実確認と、プロパガンダへの対抗はもともと、公共放送としてのBBCの責任の一部でしたが、この10年間、より多くの人がSNSからニュースを得るようになり、うわさやデマ、偽情報が蔓延(まんえん)する余地が生まれています。
私たちは長年、ファクトチェック、偽情報などの検証をしてきましたが、その重要性はますます高まっていると感じています。
――BBC Verifyを始めた理由は何ですか。ファクトチェックは、どのように変わりましたか。
BBC Verifyは2023年に発足し、私たちの番組やニュースで使われる情報や映像なども検証しています。BBC Verifyの立ち上げにより、事実確認、検証、偽情報の調査という仕事が、BBCの報道においてより重視されるようになりました。
今後は、BBC Verifyの記事をあらゆるプラットフォームで配信し、BBCのジャーナリズムがどのように作られているかをより明らかにすることで、信頼を築くことを目指しています。
――BBC Verifyの態勢について教えてください。
BBCVerifyチームでは、約60人のジャーナリストが働いているほか、世界中にいる同僚たちとも協力しています。オンライン調査、検証、ファクトチェック、データジャーナリズム、偽情報の取材などの専門スキルを持つメンバーを集めました。
たとえばVerifyでは、ケニアとインドにもメンバーがいます。2024年の米大統領選では、ワシントンDCにもチームを設け、今も米国に関する記事を配信し続けています。
私たちの記事の多くは、42言語で翻訳されています。
―AIの台頭が目覚ましく、動画のフェイク検証やファクトチェックは不可欠です。どうやっていますか?
さまざまなオープンソースのツールを使って、画像や映像を検証し、地理的な場所を特定します。画像が以前に別の場所で使用されたことがあるかを調べるために、その画像を使ってネット検索することや、衛星画像を使って調査結果を確認することもあります。
AIによって生成されたビデオ、画像、音声はますます洗練され、視聴者が惑わされる可能性が高まっています。AIが生成した疑いのあるコンテンツを調査するために利用可能なツールは多岐にわたります。
私たちは合成メディアの専門家と協力して素材の分析を支援し、BBCの研究開発チームはディープフェイク検出ツールの開発に取り組んでいます。
コンテンツをAIで生成する側が進歩するにつれて、検出のためのツールも追いついていく必要があります。
――ファクトチェックは労力がかかるわりに読まれず、どう経営的に成り立たせるかも課題と言われます。BBCは公共放送ですが、Verifyの予算化や収益化についてお聞かせください。
BBC Verifyのコンテンツを収益化する具体的な計画はありませんが、BBCのジャーナリズムに資金を供給するために、英国外の市場でBBC Newsのアウトプットを拡大し、より多くの商業収入を生み出そうと考えています。
――プラットフォームやIT企業とのパートナーシップがあれば教えてください。
様々な技術や独自のツールを業務で使用していますが、プラットフォームやIT企業とBBC Verifyの正式なパートナーシップはありません。
――BBC Verifyの今後の目標は?
BBC Verifyの存在感をBBCの発信全体に広げ、視聴者と信頼関係を築き、24時間態勢でより多くの世界を取材できるようにすることを目指しています。
――ファクトチェックとBBC Verifyに取り組んでから、視聴者との関係では、どのような変化がありましたか?
私たちの視聴者調査チームは、2024年の英米の選挙に先立ち、視聴者や一般市民を対象に多くの調査をしました。その結果、政治家に対する信頼の欠如にあおられたニュースのなかで、偽情報についての懸念が高いことがわかりました。
英国のメディア規制機関OfComは、誤報や偽情報をめぐる成人の行動や態度について独自の調査を行い、次のような結果を得ました。
「英国の成人の約4分の1(26%)が、ファクト・チェッカーのウェブサイトやツールを少なくとも一度は利用したことがあると答えている。BBC Verifyは、5人に1人が少なくとも1回は利用していると答え、20人に1人が定期的に利用していると答えている」
――どうしてAFPではファクトチェックに力を入れるようになったのですか。
あらゆるジャーナリズムがそうだと思いますが、ファクトチェックのように事実確認をして伝えるということは、常にAFPの核、DNAにあったんだと思います。
ただ、専門部署を作ったのは2017年です。前年の米大統領選で偽誤情報が課題となり、2017年の仏大統領選を前につくりました。
いまでは世界で150人のジャーナリストがいて、26言語で偽誤情報について取材しています。このアジア太平洋地域ではヒンディー語やタイ語など8言語をカバーしています。
多くの偽誤情報は、現地語で拡散しています。なるべく地元の記者に、どのように一次資料にあたるかから、デジタルの調査報道技術まで学んでもらうようにしています。
――どれくらいファクトチェックの記事を出していますか。
月に600~700本のファクトチェックの記事を出していますが、特に多いのは選挙や大ニュースのタイミングですね。
最近でいえば、ウクライナやガザなどをめぐってはたくさんのファクトチェック記事を出しました。
――対象にするべき偽誤情報はどう選んでいますか。
ファクトチェックのジャーナリズムで難しいのは、何を調査するべきかを選定することかもしれません。あまりにもたくさん偽誤情報があるからです。
実際に誰かの暮らしに被害が出やすい偽誤情報を中心に取り上げることにしています。具体的には投票活動に影響する政治、気候変動、そして命にかかわる健康にまつわる情報です。
同時に、私たちはそれがどれだけの範囲で広がっているかも確認します。そこは世界にまたがる通信社の強みを生かせているかもしれません。
あくまでも偽誤情報を否定することが狙いです。その情報がまだ届いていない地域があれば出しません。偽誤情報そのものをむやみに広げないように意識しています。
――ファクトチェックの記事は労力がかかるけれども、あまり読まれない傾向があるといわれています。どう経営的に成り立たせていますか。
私たちの通信社は一部、フランス政府からの資金が入っています。また通信社として記事や写真、動画を配信している先のメディアでもファクトチェックに特化して購入してくれるところもあります。
ただ大きな顧客は、IT企業です。たとえば(フェイスブックを運営している)メタは、プラットフォーム上に正しい情報を流す状態をつくるために、彼らのプラットフォーム上にある情報のファクトチェックに対して対価を払ってくれています。米大統領選をきっかけに生まれた提携ですが、何をどう、いつ書くかという編集権は私たちが持つ形です。
提携の形は、IT企業ごとに違って、TikTokの場合は、誤った情報を見つけた場合にどう対処するかはTikTok側の判断になっています。誤っているとラベルを貼ることもあれば、それをプラットフォームから外すケースもあります。
グーグルは、メディアリテラシーを高め、自らがファクトチェックをしていけるように、私たちがシンクタンクや大学などでジャーナリストや教育者、学生たちに対して行っている研修を金銭的に支援してくれています。

――AIの発達に伴い、動画や写真を含め、ますます偽誤情報が発信されやすくなっている状況があります。
私たちは、こうしたディープフェイクを検知するツールも独自に開発し、利用しています。
AIによってあっという間に偽誤情報が作られていくので、スピード感は重要ですが、ファクトチェックする側はAIによるツールで確認するのだけでは不十分で、別の根拠をあげるために、ふだんのジャーナリストとしての活動で実践している手法も不可欠だと考えています。
たとえばミャンマーで地震があったとき、AIによって作られた壊れた建造物の写真などが出回りました。現地にいた報道機関として現場に行って、そんなことが起きていないことを目で確かめ、そう報じました。
私たちの活動は、すべてジャーナリストの原則にのっとっており、基本動作として現場に行く、電話をかけて裏をとる、そういう積み重ねが重要だと思っています。
――発信にあたってはどんな工夫をされていますか。
多くの偽誤情報は、視覚的であるという特徴があります。(一般的な記事のように)テキスト情報があるよりも、動画があったり、ビジュアルなイメージがあったりする方が、人々に響きやすく、拡散されやすいのです。
スペインのファクトチェックグループにならって、私たちもそういうビジュアルに似せて読ませるという手法をとりいれています。
赤い文字、たくさんの写真などを使って、まるで偽誤情報そのもののような形態で、ファクトチェックされた情報を流すのです。読者に届けることにこそ意味があり、私たちなりのアウトリーチの手法ともいえます。
メタとの関係では、たとえばインスタグラムやフェイスブックで偽誤情報があった場合には、それを見た人に優先的にファクトチェックされた情報が届くようにしてもらっています。必要な人に情報が届くようにするための仕掛けです。
――反響はどうですか。
ファクトチェックの場合、ほとんどの反応がネガティブなものです。ジャーナリズムとして「何かが誤りだ」というわけで、挑戦的に受け止められがちです。だからハラスメントとも受け取れるような反響も寄せられます。
ただ、ごくごくたまにですが、「ありがとう」といった反響も寄せられます。そういうときは、わざわざ連絡してくれる人が限られるだけで、こういう風に感じている人はほかにもたくさんいるんだと思うようにしています。そしてそういうメッセージはチームと共有します。
ファクトチェックをする立場としては、人が何かを決めるときに事実に基づいて判断できる状態をつくりたい、という思いが強いです。誰かの意見を変えたいと思っていません。もし私たちの取材の根拠が違うなら、それをそう指摘してほしいと思っています。
――将来目指すことは。
ファクトチェックはまだ始めて10年、20年といった新しい分野です。でも、分断されていく社会で、私たちを信頼しないと言っている人たちに対しても含め、私たちが取材した情報を提供していくことが公共的使命だと思っています。
今の時代のような分断があるということは、そこに空白があるということです。メディアには(情報や認識の違いにつながる)その空白を埋める役割があると考えています。
メディア側もかつては、私たちはこういうメディアだ、これがスクープだ、と一種のエゴがあったのではないかと思います。
私たちが誰のために、なぜ書いているのかを考えれば、おのずと(ファクトチェックの重要性が)見えてくるはずです。まずは私たち自身、信頼を得る必要があります。
そして、取材した情報を発信するだけではなく、必要とする人に読んでもらえるようにしていくことまでを仕事としてやっていくことが重要です。