江戸時代の人は『千と千尋』に共感できない?
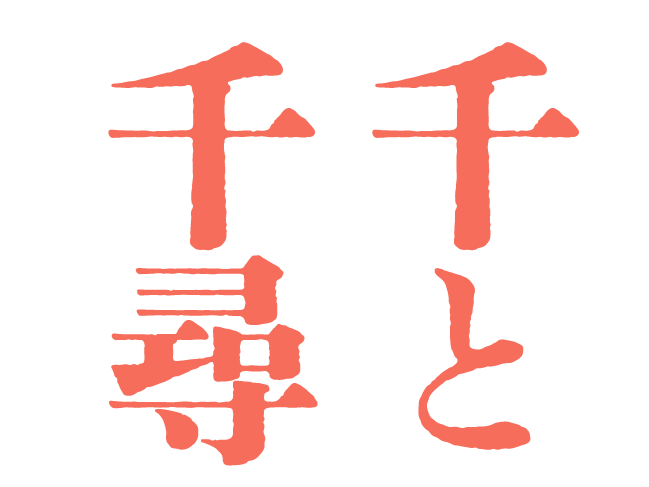
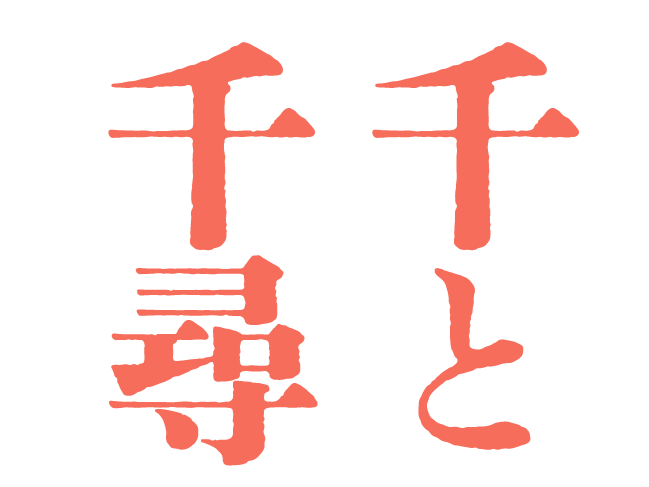
名前はかけがえのないものである。個性を表すものでもある。私たちはそう信じて疑わない。
ジブリ映画の『千と千尋の神隠し』で主人公の千尋は、湯屋の主人、湯婆婆に名前を取り上げられ、「千」として働かされる。「なんてひどいことを!」。しかし多くの試練をくぐり抜け、物語の最後で名前を取り戻す。「本当によかった!」
奪われた名前を取り戻す。それはハッピーエンドである。私たちは、自然にそう思えているから、物語の展開に共感できる。だが――。
「江戸時代の人は共感できないでしょう」。神戸大経済経営研究所で研究員を務める尾脇秀和さん(42)は言う。江戸時代にはそもそも、「大切な唯一の名前」という感覚がなかったからだ。「かけがえのあるものだったのです」

江戸時代、名前は社会的な地位を表した。地位や職を表す通称が名前として機能し、例えば寛政の改革で有名な老中松平定信は「越中守(えっちゅうのかみ)」と呼ばれていた。教科書で習う「定信」は通常、名前として使われなかったという。
職と地位が変われば、名は変わる。「江戸時代の人からすれば、奉公するなら千に変えられるのも当然でしょ、という気持ちでしょうね」
変革は、明治時代に起きた。国民国家として進むためには、名前の管理が必要だった。徴兵も、税金の徴収も、誰がどこに住んでいるのかを把握しなければできない。肝心の名前が頻繁に変わるようでは把握に差し支えるので、1872年には改名が禁止される。国家の発展のためだった。
「坂の上の雲」の時代。国民意識が高まっていた。「近代の国民には国家に把握された変わらない名前が必要だという認識が強まった」と尾脇さん。戸籍に登録した名前は唯一不変であるべきだ。ここに、日本人が現在まで連綿と抱く「私の大切な名前」という愛着が生まれる。
戦後、憲法がこの流れを後押しした。13条には個人の尊重がうたわれた。大事なのは家ではない。個である。「名前は、親という個人の教養や趣味が反映されるものになった」。親の思いが込められたかけがえのない名前に、愛着は深まり、愛着は自身のアイデンティティーにつながる。ますます自分の名前にこだわるようになる。
戸籍には、誤字や「髙」などの俗字が登録されていることが多い。1990年代に、この誤字や俗字を市区町村長の権限で正字に書き換えられるようにする動きがあった。しかし、誤字でも俗字でも、大切な授かり物だ、と反対の声が上がり、中止された。事務上の合理性よりも愛着が優先された。
尾脇さんは言う。「今の時代は個人や多様性を重視する社会になっている。当然、現代の文化として名前への愛着をむげに否定すべきではない」。それでも、と続ける。「その価値観は普遍的ではなく、過去には今とは異なる名前の文化や価値観があったと理解することは大事だと思います」
時代によって社会は変わる。その変化に合わせて、名前のかたちにもこの先、新たな変化が生まれるかもしれない。そのとき、私たちはまだ名前に愛着を持っているのだろうか。